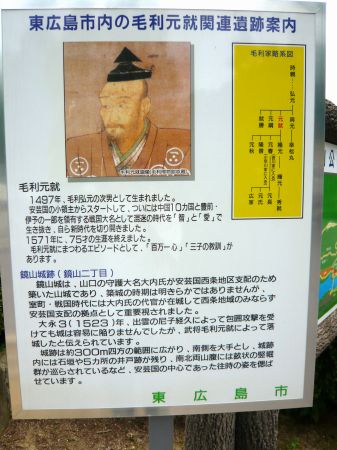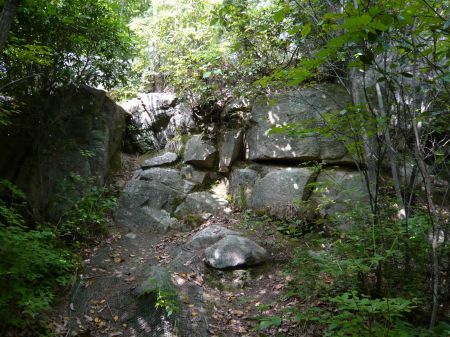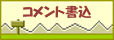|
鏡山公園入口。
バックは鏡山。
|
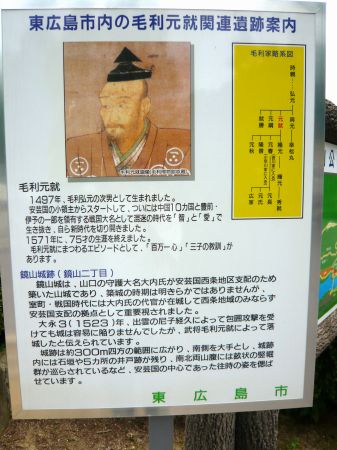 |
最近、少しでも元就に関係ある城跡には、
この手の案内板が設置されている。
|
 |
その横にある案内板。
|
 |
登山中、東出丸。
この後、「竪堀」の案内板があるが、
藪で確認出来ない。
|
 |
堀切。(案内板有り)
堀切の中から尾根側を向く。
|
 |
5郭(下のダバ)。
2郭のすぐ東下ですが、
急峻な崖下(13m)となっています。
井戸跡があります。
|
 |
その中を覗く。
|
 |
4郭(大手門跡)。
この下に南郭群が存在します。
とりあえず下りてみる。
|
 |
南郭群に下りる途中、
3郭(馬のダバ)下の石垣。
|
 |
そのすぐ先左手遥か下方に、
横に細長い郭と、左端にはその郭に向かって
竪堀が伸びています。
|
 |
そのすぐ先右手に畝状竪堀。
写真では分かり難いが、4本の竪堀が確認出来る。
|
 |
振り返って小郭。
2つ前の写真の郭の西側辺りに位置します。
|
 |
その南下に小郭。
|
 |
そのすぐ先右手に南郭群最大の郭でしょうか。
|
 |
上記郭南に土塁跡。
|
 |
そこからすぐ車道に出ます。
左の階段から下りて来ました。
この周辺は牧場になっており、平地です。
|
 |
大手門跡まで戻り、3郭(馬のダバ)へ。
その入口にある門跡。
|
 |
3郭(馬のダバ)。帯郭の形をしています。
2郭のすぐ南下ですが、
やはり急峻な崖下(13m)となっています。
|
 |
2郭(中のダバ)。
軽く3段になっています。
南(左)側には土塁があります。
井戸跡が2つあります。
|
 |
ここの井戸跡は2基とも窪みしか残っていません。
|
 |
2郭から北郭群目指して下ります。
途中、直進と右下とに分岐していて、
奥の方には井戸跡が見えます。
とりあえず直進。
|
 |
そのすぐ先、右に竪堀が下っています。
|
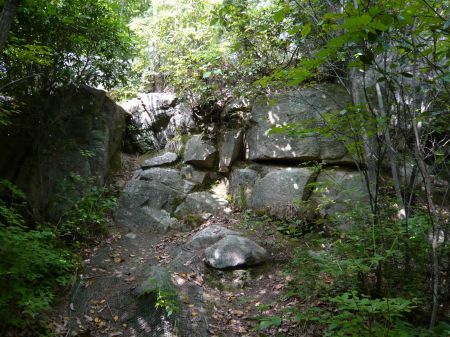 |
1郭(御殿場)西下の石垣。
がんばれば、この岩を伝って御殿場に登れます。
ここから1郭2郭(山頂部分)をトラバースする様に
南側に山道があったのですが、
多分、3郭(馬のダバ)に続いているのでは...
|
 |
振り返ると北端が岩になっている小丘陵。
多分見張り台だったのでは?...
|
 |
その先の小丘陵との間に堀切。
|
 |
更に西へ行くと、また堀切。
|
 |
その先に小郭。
やはり北端に岩が...
見張り台?...
ここから引き返し、先ほどの分岐を下りてみる。
|
 |
北郭群と書いてあるが、
ただの北郭群最大の郭でしょう。
|
 |
上記東に竪堀跡が上から下へ。見下ろす。
この先(東)にも郭がある様ですが、
藪なのでパス。
|
 |
先ほどの郭のすぐ北下にある郭。
|
 |
そのすぐ下に小丘陵。
ここから2郭(中のダバ)まで引き返す。
|
 |
1郭(御殿場)。
東の高所とそれを取り巻くL字型の低所の
2段になっています。
建物跡があり、御殿があった様です。
|
 |
御殿場西の岩場から西側方面。
奥は鉾取山山系でしょう。
右端の方に見えるのが、
曽場ヶ城山(曽場ヶ城跡、一ツ城跡)で、
正面奥の方が槌山城跡でしょう。
|
 |
同じく南側方面。
左の方の山を越えると小早川領で、
松尾城跡等があります。
|
 |
鏡山城全景。(北側より)
|
(まとめ・総評)
大内氏が安芸、備後の拠点として築城。
毛利氏がまだ尼子側に就いていた際、尼子経久によって攻められる。
元就は、病弱の毛利当主幸松丸(元就長兄亡興元の子、9歳)を後見し、参戦。
兄倉田備中守、弟倉田日向守が堅固に守っていて容易に落ちなかったが、
元就の謀計で日向守を謀反させ、落城。これが因で、付近の大内方国人は揺れ動く。
尼子経久によって、元就の功は認められたが、結局日向守は斬首された。
この年、幸松丸は病死(鏡山攻城参戦が因とも...)し、元就が家督を継ぐ。
国道2号線(西条バイパス)から降りて、広大方面を目指して南下。
広大手前で鏡山公園(案内表示有り)があり、その駐車場に車を置き、登る。
山頂まで寄り道無しなら15分くらいのものですが、今回のコースでよく見て回って1時間ちょっとです。
南郭群は麓近くにあり、大手道の防備の為のものでしょう。
北郭群は、比較的緩斜面の北側の防備と、搦め手道の監視の役目だったのではないでしょうか。
今回は2回目の登城ですが、前回(2006.4.6)の右も左も分からない時と違い、資料に頼らず多くを探訪出来て、
新鮮な部分も多々あり楽しめました。
|