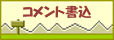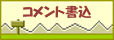| 二ノ丸~西出丸~奉行丸~平左衛門丸 |
 |
まず二ノ丸駐車場に車を停めて、
広大な二ノ丸を仰ぐ。
|
 |
そこにある案内板。
|
 |
西出丸長塀の外側。
|
 |
奉行丸長塀の外側。
|
 |
枡形の西大手櫓門。
正面と右は元太鼓櫓。
|
 |
西出丸。
|
 |
西出丸長塀には鉄砲狭間がずらりと...
|
 |
奉行丸。
右奥は未申櫓。
|
 |
西出丸の南大手櫓門から外に出て、振り返る。
鉤型になっています。
|
 |
備前堀。
|
 |
右から宇土櫓、大天守、小天守。
|
 |
その下は深い堀に...
|
 |
料金所前の案内板。
ここから入場料が必要です。
|
 |
高い石塀の間を...
|
 |
鉤型に縫って行くと...
|
 |
大天守、小天守がそびえ立つ。
|
 |
左を向いて、平左衛門丸と宇土櫓。
|
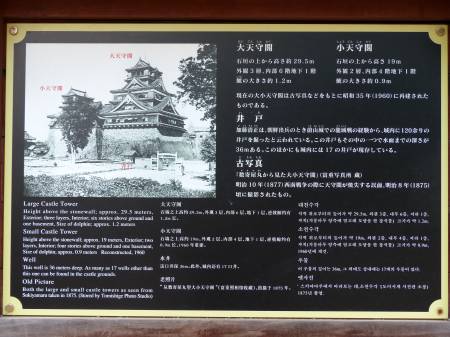 |
大天守、小天守の説明板。
|
 |
平左衛門丸南端に、五郎の首掛石。
築城時に横手五郎なる人が、
1800キロあるこの石を首に掛けて運んだとか...
|
 |
五郎の首掛石から10m南に、地図石。
この整然と並べられた石の意味は諸説あるが、
結局確かな所は???
|
| 平左衛門丸~飯田丸~竹の丸~東竹の丸 |
 |
平左衛門丸から数寄屋丸の横を下って行きます。
|
 |
幾度か折り曲がると...
|
 |
質部屋跡。
奥は飯田丸。
|
 |
二様の石垣。
右が加藤時代の乱れ積み、
左が細川時代の布積み。
左の方が勾配がきつい様です。
|
 |
そして、そこから天守閣を仰ぎます。
|
 |
更に鉤型に下って...
|
 |
振り返る。
|
 |
五階櫓跡。
|
 |
石垣の各所に排水口が見えます。
|
 |
竹の丸。
|
 |
そこの長塀。
|
 |
竹の丸東端に平御櫓と鉤型。
|
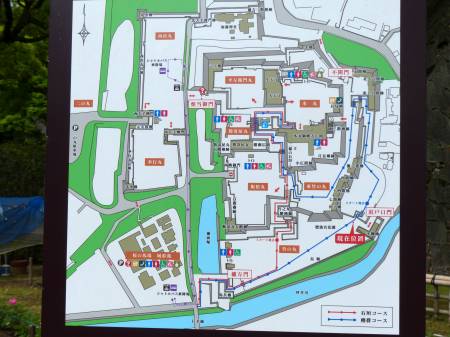 |
そこにある案内板。
これが一番詳しく書いてあります。
|
 |
東竹の丸の櫓群を見上げる。。
|
 |
東十八間櫓。
|
 |
そこからまた登り返しになります。
|
 |
コの字型に曲がって登ります。
|
 |
五輪塔。
|
 |
五間櫓、北十八間櫓。
|
 |
不開門(あかずのもん)を出て振り返ると、
やはり鉤型になってます。
|
 |
ここで振り返ると石垣の上に平櫓が見えます。
|
 |
東竹の丸。
|
 |
東竹の丸にある、現之進櫓、四間櫓辺り。
更に奥に十四間櫓、七間櫓、田子櫓と続く。
|
| 東竹の丸~本丸御殿地下~本丸 |
 |
しつこい様ですが鉤型に上って...
|
 |
闇り通路に突入!
本丸御殿の地下になります。
闇り通路はこんなになってます。
┏━━━
┃ →平左衛門丸
┃ ┏━
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
━━┛ ┗━
月見櫓跡← →本丸
━┓ ┏━━
┃↓┃
東竹の丸
|
 |
まずは月見櫓跡に寄って、東竹の丸を見下ろす。
奥は、先ほど見た、
現之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓。
|
 |
戻って本丸へ...
天守閣の雄姿!
|
 |
天守閣の中に入って、城下町の模型。
|
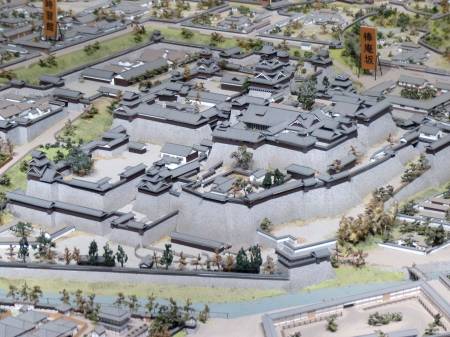 |
主郭辺りをアップ!
|
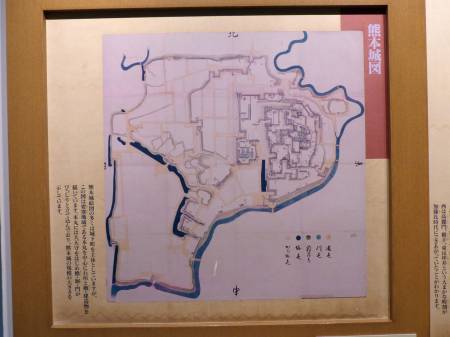 |
熊本城図。
|
 |
骨組みの模型。
|
 |
天守閣の中は完全に資料館になってますが、
一部石垣などは保存されています。
|
 |
最上階から平左衛門丸を見下ろす。
右に宇土櫓、
奥に奉行丸長塀、西出丸長塀が連なって見えます。
|
 |
本丸を見下ろす。
右が本丸御殿、
中央に大銀杏が見えます。
大銀杏は加藤清正自らが植えたと言われますが、
これは西南戦争で焼失した跡から出た
二代目だとか...
|
 |
東の展望。
|
 |
南の展望。
|
 |
南西の展望。
|
 |
北西の展望。
|
| 本丸~本丸御殿地下~平左衛門丸~二の丸 |
 |
闇り通路を平左衛門丸方面へ...
|
 |
闇り通路を出て、振り返る。
|
 |
天守閣を南側から見上げる。
|
 |
城内を一周して、
平左衛門丸にある案内図。
|
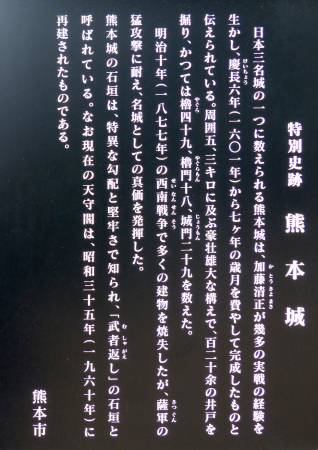 |
熊本城説明板。
|
 |
二の丸に戻って、
西出丸長塀越しに宇土櫓、小天守、大天守。
|
(まとめ・総評)
石垣普請の名手とされる加藤清正の築城。
加藤清正は、関ヶ原合戦の功により肥後52万石の領主となる。
西南戦争で天守や御殿、櫓などの主要建物を焼失。
石垣は、
明治22年の熊本地震での一部が崩れ、改修されているが、ほぼ江戸期のままの姿を留めている。
闇り通路は、
元は本丸を南北に分ける単なる石垣の通路であったが、その上に本丸御殿を建築し、地下通路となった。
現存遺構は、
宇土櫓、長塀、不開門、平櫓、東十八間櫓、北十八間櫓、五間櫓、源之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓。
|