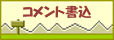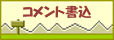| 資料館横のPから内掘外を回って大手門へ... |
 |
内堀。
資料館横の橋から南側。
|
 |
内堀。
西端から大手門側。
|
 |
大手門側から天守を仰ぐ。
木が茂って見え難いですが全面石垣。
|
 |
大手口。
目の前は大手二の門。
|
 |
二の門の裏に鉄砲狭間。
|
 |
二の門から枡形に曲がって大手一の門。
この2つの門も往時から存在するものです。
|
 |
一の門を潜って左手に案内板。
|
| 見返り坂を登って、三の丸、二の丸、本丸へ... |
 |
見返り坂。
これを登って、三の丸へ向かいます。
|
 |
三の丸石垣の北の角。
|
 |
上記別角度から。
|
 |
三の丸東側。
|
 |
三の丸から見る讃岐富士(飯野山)。
|
 |
三の丸北にある櫓跡から瀬戸大橋方面の展望。
|
 |
三の丸から二の丸へは、
登りながら鉤型になっています。
この二の丸入口の石垣には、
櫓門が渡されていたのではないでしょうか。
|
 |
二の丸。
|
 |
二の丸にある井戸跡。
|
 |
覗いてみる。
深さ65m、海抜より低く、
日本一深い井戸とも...
|
 |
二の丸から本丸へも鉤型になっています。
この石垣にも櫓門があったのではないでしょうか。
|
 |
本丸。
|
 |
現存天守を見上げる。
現存十二天守の中では最小だそうです。
|
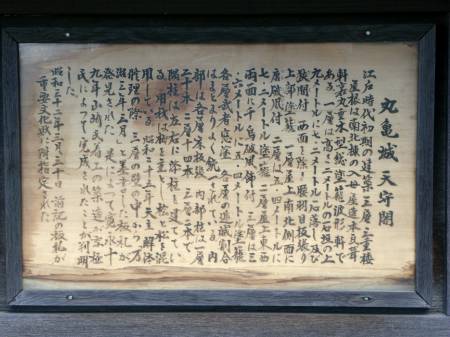 |
その説明板。
|
 |
第一層の天井。
|
 |
鉄砲狭間と石落しの蓋です。
|
 |
第二層。
|
 |
第三層、最上階です。
展望は格子窓からだけです。
|
 |
格子窓から東側の展望。
|
 |
天守閣の北西面。
台風の被害で修復中です。
左下は三の丸、
中央奥石垣の上は二の丸、
そこへ続く道(現在通行止)は二の丸搦手口です。
|
 |
本丸から東側の展望。
|
 |
足元に三の丸の井戸跡が見えます。
|
| 三の丸を西回りで一周して搦手口へ... |
 |
三の丸より二の丸北隅の石垣。
|
 |
二の丸北西面の石垣。
|
 |
天守閣を正面からですが、残念!
|
 |
大手門少し左手、
藩主玄関先御門や番所長屋跡が見えます。
|
 |
更に左を向いて、
この芝生広場辺りに藩主の館があった様です。
|
 |
先程本丸から見えた三の丸の井戸跡です。
|
 |
北東に移動して、こちらは二の丸の石垣です。
|
 |
こちらも二の丸の石垣ですが、
櫓台でしょうか。
|
 |
搦手を下りながら、奥は三の丸の石垣です。
|
 |
搦手口。
奥が城域です。
|
 |
そこから右手の内堀。
|
 |
左手の内堀。
|
 |
南側より、本丸南端の石垣です。
|
 |
駐車場(南西側)からも見上げます。
|
 |
帰りに与島PA(瀬戸大橋)から城跡をズーム!
|
 |
逆に城から与島PAをズーム!
約11kmある様です。
|
(まとめ・総評)
1597~1602年、讃岐国領主生駒氏により築城。
1615年、一国一城令により廃城。
1641年、生駒氏、お家騒動(生駒騒動)の為、出羽国に転封。
1642年、山崎氏、肥後国より入府、西讃岐国(讃岐国二分)丸亀藩主となる。
1643年、山崎氏により再築。
1656年、丸亀城焼失。
1657年、山崎氏、嫡子が無い為、断絶。
1658年、播磨国より京極氏が入封、丸亀藩主となる。
1660年、京極氏により再築。(これが現存する天守です。)
標高66mの亀山に築かれた平山城(丘城)。別名亀山城とも...
本丸、二の丸、三の丸、帯郭、山下郭から成り、天守は現存十二天守の1つ。
日本一の高さを誇る石垣は「石の城」と形容され、全国に名をとどろかせる。
|