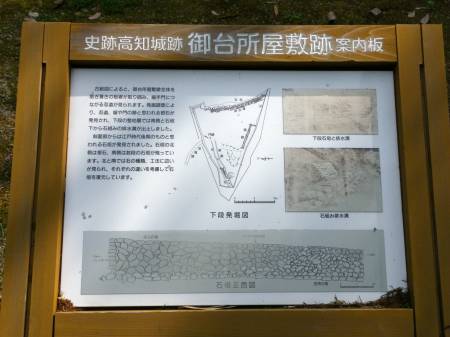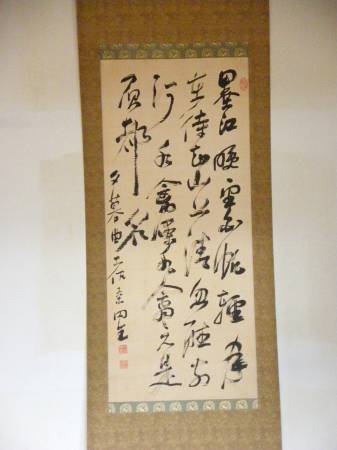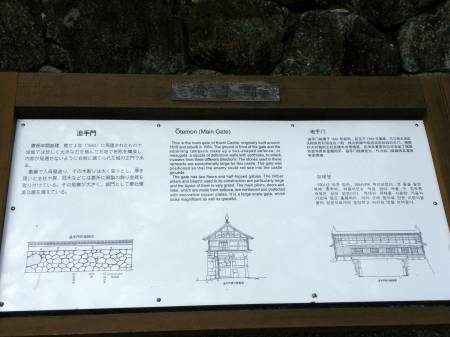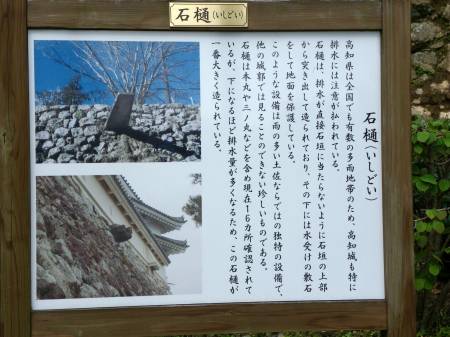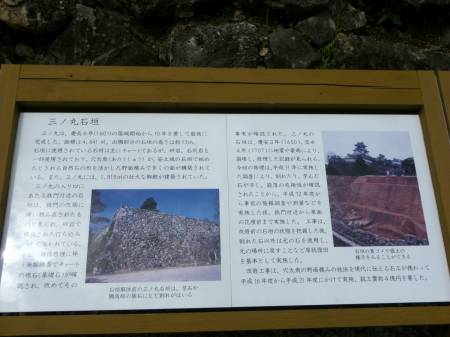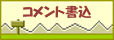| 御台所屋敷跡(西側)から本丸へ... |
 |
御台所屋敷跡、上下段の間の石垣跡。
|
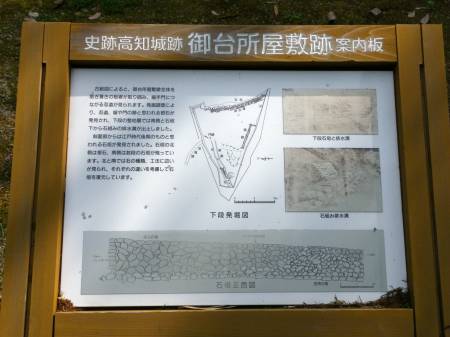 |
その石積みや排水溝の説明。
|
 |
石垣は、下部は当時のまま、上部は復元です。
|
 |
下の段西端の土塁。
|
 |
上の段。
奥に天守閣、黒鉄門が見えます。
|
 |
そこの説明板。
|
 |
御台所屋敷跡から二ノ丸に向かう通路の左下、
何気に大きく立派な石垣があります。
|
 |
獅子の段から二ノ丸の石垣。
右奥は詰門。
|
 |
二ノ丸。
中央奥に天守閣。
|
 |
別角度から...
|
 |
二ノ丸の説明板。
|
 |
「高知城懐徳館入口」とある。
橋廊下と呼ばれ、詰門の上部にあたります。
|
 |
その中。
|
 |
そして出口、廊下門。
|
 |
振り向くと天守閣と本丸御殿。
ここはもう本丸です。
|
 |
本丸、天守閣の説明板。
|
 |
控え柱と鉄砲狭間。
控え柱の間に板を渡し、
その上から鉄砲を撃ったとも...
|
 |
本丸裏門にあたる黒鉄門。
非常時用の門で、各所に鉄板が打ち付けられ、
黒く塗られた事からこう呼ばれた。
|
 |
いつの時代の写真でしょうか...
|
 |
本丸御殿の中。
奥は上段ノ間(藩主の御座所)です。
向かって左手には納戸(武者隠し)が有り、
裏から回って見学出来ます。
|
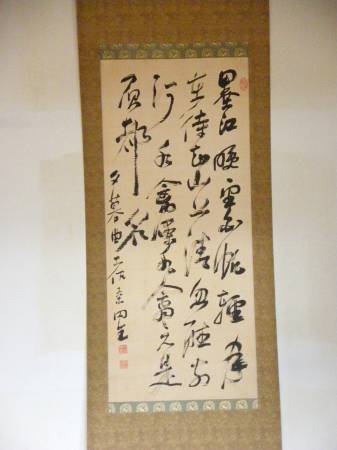 |
十五代藩主 山内豊信(容堂) 詩書「夕暮曲」。
(複製)
|
 |
城と城下町の模型。
少しデフォルメされてます。
|
 |
本丸、二ノ丸、三ノ丸周辺の模型。
|
 |
少し範囲を広げて、内堀内の模型。
|
 |
鯱瓦。
|
 |
天守最上階。
|
 |
三ノ丸方面の展望。
|
 |
二ノ丸方面の展望。
二ノ丸から橋廊下(詰門)を渡り、
廊下門を潜って本丸に至る経路が確認出来ます。
|
 |
本丸、黒鉄門、本丸御殿の屋根々々。
|
| 追手門(東側)から三ノ丸へ... |
 |
追手門。
高知城の大手になります。
|
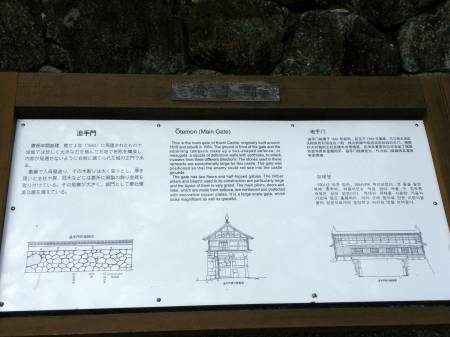 |
その案内板。
|
 |
追手門近くの内堀。
外堀は、
北に江ノ口川、久万川、
東に堀川、国分川、
南に鏡川を
天然の堀としていたのではないでしょうか。
|
 |
山内一豊像。
|
 |
石樋。
|
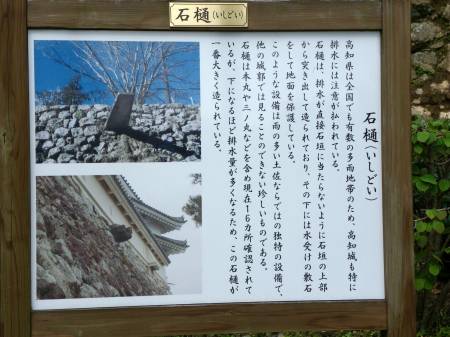 |
その案内板。
|
 |
杉ノ段より三ノ丸石垣跡。
|
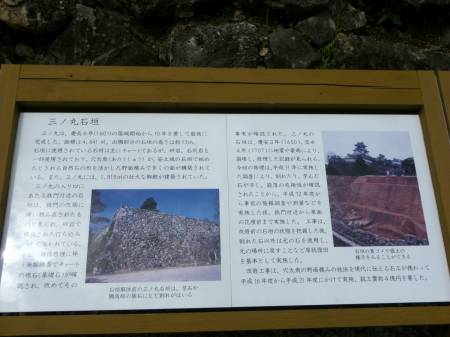 |
その案内板。
|
 |
別角度から...
野面積みですが、
角の部分は加工されている様です。
|
 |
鉄門跡。
この門を潜ると、左に枡形になっており、
正面と右上は三ノ丸になってます。
ここまで攻め上がると、渡門上と三ノ丸の三方から
攻撃を受ける仕組みになっています。
|
 |
詰門。
鉄門を過ぎると、正面にこの門があり、
本丸へのダミーと考えられます。
実際は、門手前で右折して、
二ノ丸経由でないと本丸には行けません。
|
 |
詰門前(東側)から天守閣を仰ぐ。
|
 |
近付くと石落しや忍び返しが確認出来ます。
|
 |
三ノ丸。
このすぐ上から二ノ丸、本丸へと続く...
|
 |
その案内板。
|
 |
鐘撞堂(本丸から南)下の石垣。
|
(まとめ・総評)
関ヶ原合戦後、山内一豊がこの地に入り、築城した城。
南北朝時代や長宗我部時代にもこの地に城は存在したが、現在の高知城築城は山内一豊による。
当初浦戸城に入った一豊は、高知城築城を開始、2年後に本丸、二の丸が完成し、移転、
更に8年ほどを掛けて三の丸を含むほぼ全域が完成した。
その116年後、火災により追手門以外のほとんどを消失、2年後から25年かけて全城郭を再構築した。
(現存する遺構はこの時のものです。)
明治4年の廃藩置県後、明治6年に本丸の建物と追手門以外全て取り壊され、
明治7年に公園化、一般公開された。
昭和9年、国宝に指定。
土佐の地は雨が多く、高知城は排水の機能が多く目立つ。
杉ノ段に登る途中に見られる石樋、御台所屋敷跡に残る排水溝跡、
排水性の良い野面積みの石垣などなど...
|