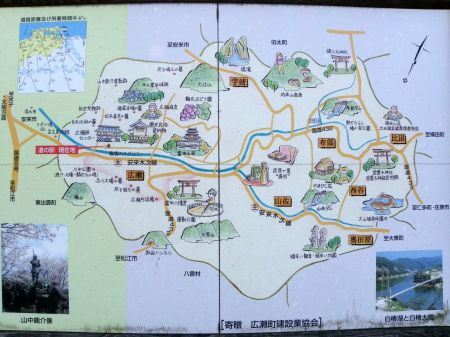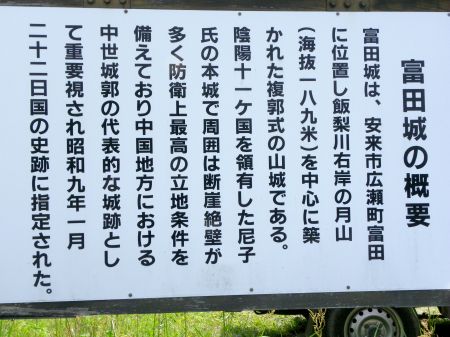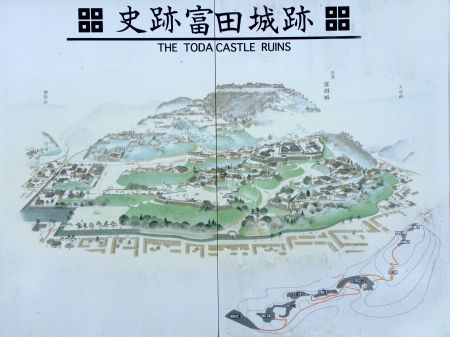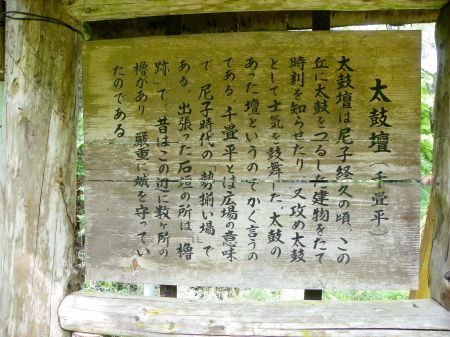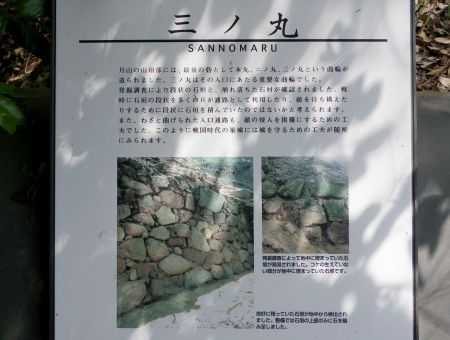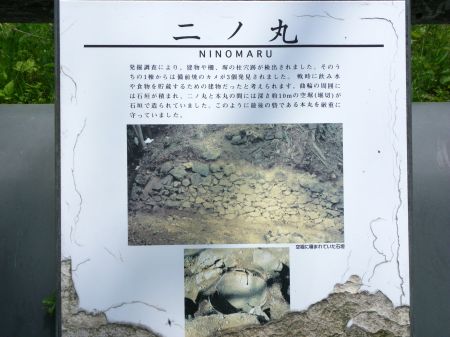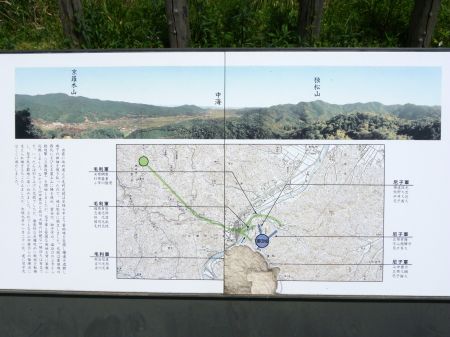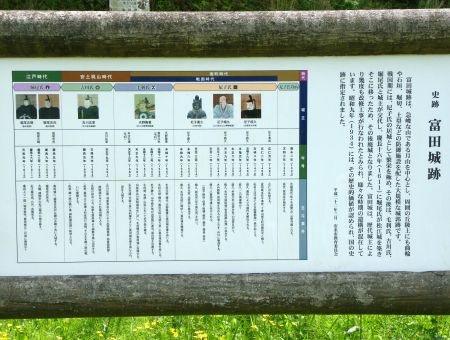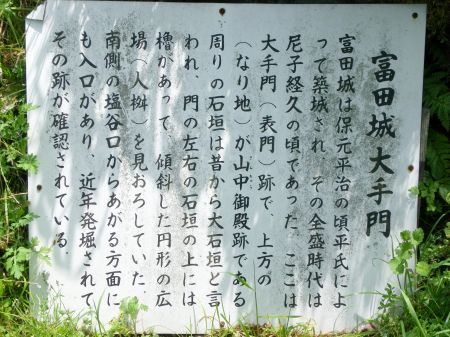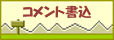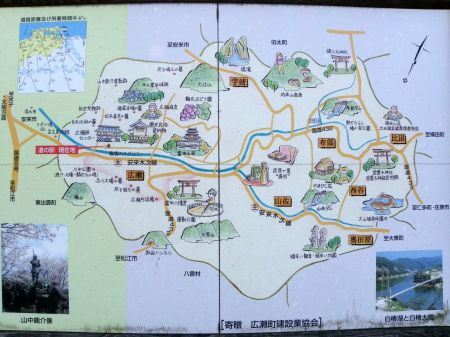 |
富田城道の駅周辺の地図。
|
 |
富田城周辺の地図。
|
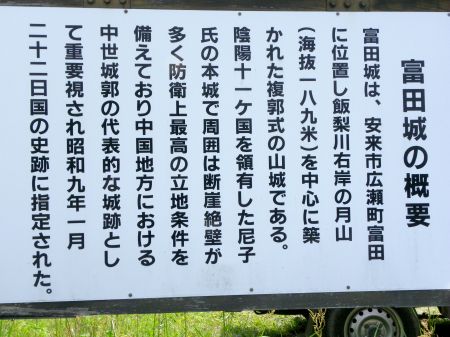 |
富田城の概要。
|
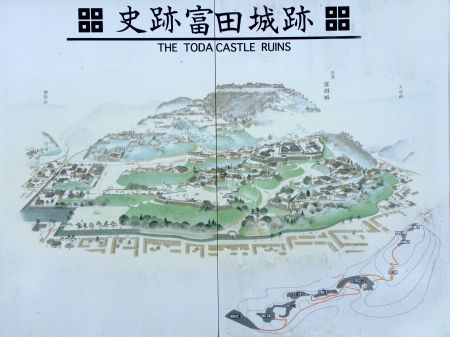 |
富田城郭図。
以上、道の駅にて...
|
 |
道の駅から山側(南東)に進むと、
すぐに尼子興久の墓。
|
 |
千畳平に向かう途中、馬場跡。
|
 |
千畳平。
|
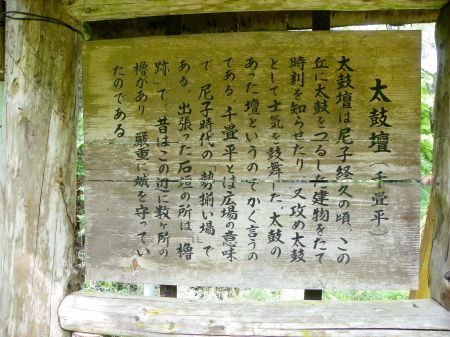 |
その説明板。
「太鼓壇(千畳平)」となっているが、
他の案内では、ここが千畳平、
南東1段上が太鼓壇となっている。
|
 |
千畳平西端にある椎の木。
樹齢400年以上で、毛利氏による兵糧攻めの折り、
少なからず食料の足しになったと考えられます。
|
 |
千畳平と太鼓壇の間の高所。
見張り台的な郭でしょうか?
|
 |
その1段下(太鼓壇側)の郭。
|
 |
太鼓壇。
|
 |
そこにある山中鹿之助(鹿之介)(鹿介)像。
|
 |
奥書院平。
|
 |
花ノ壇(侍所)。
|
 |
その説明板。
写真は地元の小学生による発掘調査の風景。
|
 |
山中御殿北東(外側)の石垣。
|
 |
その内側。
「多門櫓跡」とある。
|
 |
山中御殿。
|
 |
その説明板。
|
 |
東にある門跡。
|
 |
その横に櫓跡。
|
 |
更に横に井戸跡。
|
 |
石垣。
この右側が山中御殿内側、
左側が菅谷口門跡で本丸へ続く。
|
 |
七曲がりの石畳。
「七曲がり」は、山中御殿から三の丸に向かう、
急斜面を登るつづら折りの道。
|
 |
七曲がり途中にある山吹井戸。
|
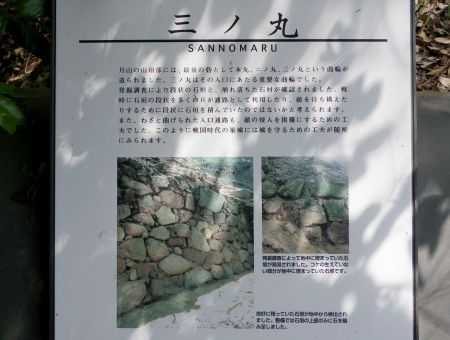 |
七曲がり終点に三の丸の説明板。
|
 |
三の丸北西下の石垣。
|
 |
三の丸虎口。
七曲がり終点から三の丸に登って振り返る。
|
 |
三の丸。
|
 |
奥に井戸跡。
残念ながら蓋がしてあり確認出来ません。
|
 |
二の丸下(三の丸側)の石垣。
|
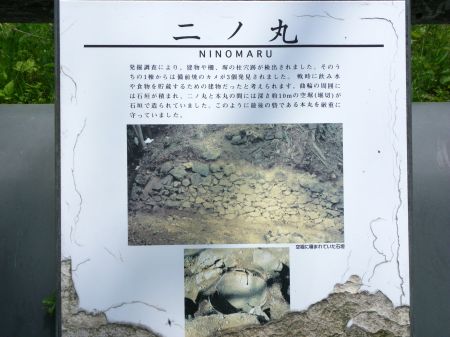 |
二の丸の説明板。
|
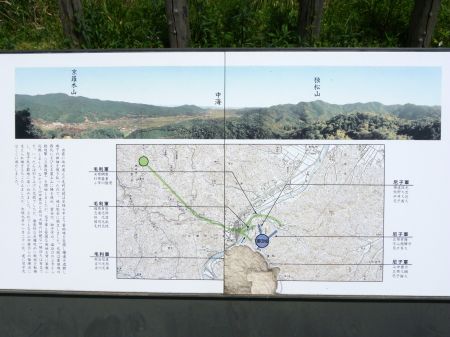 |
二の丸にある展望図。
京羅木山に陣取った毛利軍の侵攻経路(三方)と、
迎え撃つ尼子軍の動きが記してある。
|
 |
北方面の展望。
|
 |
左を向いて京羅木山。
|
 |
二の丸から本丸との間の堀切を見下ろす。
|
 |
堀切から石垣越しに二の丸を見上げる。
|
 |
本丸。
|
 |
本丸にある眺望図。
|
 |
北方面の展望。
|
 |
月山略史年表。
鎌倉時代以前の築城から江戸時代初期の廃城
までの427年の歴史が記してある。
|
 |
「山中圭或塔」。
山中鹿介記念碑との事。
山中鹿介関係の史跡がやたら多い。
パンフを見ても周辺に5ヶ所はある。
|
 |
右に土塁と左に窪地。???
|
 |
本丸北東にある土塁跡。
|
 |
一番奥には勝日高守神社。
|
 |
その裏手の石垣。
|
 |
下りは二の丸、三の丸を南へ迂回。
三の丸西下の石垣。
|
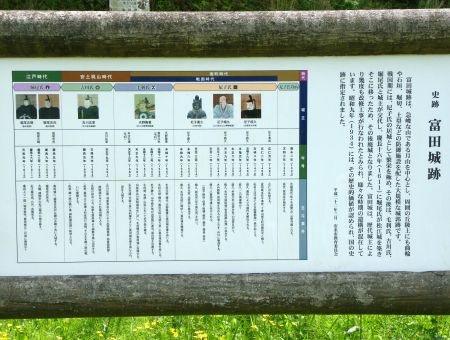 |
山中御殿にて、
富田城の城主が尼子氏、毛利氏、吉川氏、堀尾氏
と遷移してきた旨が書かれている。
|
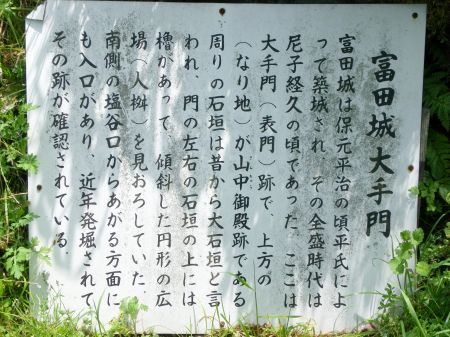 |
大手門の説明板。
|
 |
その大手門の片鱗。
|
 |
軍用大井戸。ってこれの事かな?
※追記:違うらしい...
|
 |
史跡 富田城跡 案内板。
大手門から谷筋の舗装路を通って
歴史資料館の裏まで帰って来ました。
|
 |
地形模型。
|
 |
その説明板。
|
 |
富田城城下町跡(富田川河床遺跡)の説明板。
|
 |
その富田川(飯梨川)。
有名な山中鹿之助と品川大膳の一騎打ちのあった
中州(川中島)は今は奥の土手の向こうになります。
|
 |
月山富田城跡全景。(西側より)
|
(まとめ・総評)
平安時代末期頃、平景清が富田荘に入り、八幡社を移して築城した。との説がある。
鎌倉時代初期頃、佐々木義清が出雲、隠岐二ヶ国の守護として富田城に入る。
南北朝時代、一時山名氏の領となるが、京極氏(佐々木氏)の手を経て、
室町時代初期(南北朝時代を除く)、尼子清貞(3代当主)を城主とする。
(このあたりまで情報が交錯し、定かではありません。)
以後、尼子氏の本拠として、山陰、山陽十一ヶ国を領するまでの礎となる。
長門、周防を拠点とする大内氏とは、安芸、備後などで攻防を続け、国人衆も両者間で頻繁に鞍替えする。
室町時代末期、大内氏の出雲遠征(毛利氏も従軍)を一旦退けるが、その19年後、
厳島合戦で大内氏(陶氏)を破り、勢力を拡大した毛利元就に包囲され、持久戦(兵糧攻め)の末、
7年後に落城、毛利氏家臣(一族?)の天野隆重が入る。
後、吉川元春(元就次男)の三男、吉川広家が秀吉の命で、出雲、伯耆の一部等を与えられ、入城。
関が原合戦敗戦を受けて、毛利、吉川減封後は、堀尾忠氏が入り、
その15年後、松江城完成を持って、家康の「一国一城令」により廃城となる。
城域が余りに広すぎて、現地やパンフで案内されている以外は廻っていません。
時間的な制限もあり、周辺の史跡も全てパスしました。
観光地としてかなり整備されており、石垣等はほぼ復元されたものと思われます。
七曲がりの石畳もあやしいです。
しかし、道の駅にある郭図(郭図2)等は、当時の城の雰囲気を再現して、面白いものになっています。
|