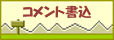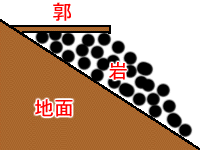|
城域は基本的に牛頭山西峰から東西鞍部までですが、
東鞍部から東峰までの間の各所にも、
土塁や石積み跡が見られます。
以下、
東鞍部→西峰(本丸)→西鞍部と順次紹介します。
|
 |
東鞍部からいきなり岩場の急登です。
|
 |
岩場を登りきると郭跡です。
↓こんな感じになっているのではないでしょうか?
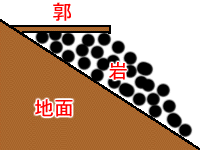
|
 |
上記すぐ一段下の郭と...
|
 |
その帯郭。
|
 |
この土塁(石積み)を登ると...
|
 |
東第五郭跡。
|
 |
その先の堀切。
中央が土橋状になっていて、
奥は上の郭に向けて切り立っています。
|
 |
その奥の郭跡。
|
 |
上記郭の縁に石積み跡。
|
 |
次の郭跡。
|
 |
更に次の郭跡。
|
 |
その奥の石積み跡。
|
 |
東第二郭跡。
|
 |
手前が東第一郭跡、奥が三の丸跡。
軽い段差はあるが、境界が曖昧。
↓右の藪の中に標柱がある。
 
|
 |
この虎口を登り切ると...
|
 |
本丸跡。
|
 |
南の展望。
中央奥が荒谷山で、
その左奥に武田山(銀山城跡)が見える。
|
 |
北東の展望。
|
 |
東の展望。
鈴張川沿いの街道が見える。
|
 |
二の丸跡。
|
 |
そのすぐ下の郭跡。
|
 |
そのすぐ下に西第二郭跡。
すると上記は西第一郭跡かな?
|
 |
西第二郭跡を先(下)から見上げる。
門(虎口)跡か?...
|
 |
その先の郭跡。
山道から左に逸れている為、藪化している。
|
 |
上記郭の下に石積み跡。
|
 |
平らな山道で右手が広くなっている。
ここも郭跡かな?
|
 |
西第一堀切跡。
左手は堀切らしいが、
右手は単なる斜面で堀切らしくない。
|
 |
西第三郭跡。
|
 |
その下の石積み跡。
|
 |
山道右手に怪しい岩が...
|
 |
登って見ると...
西鐘の段跡。
|
 |
登城路があったと思われる(想像ですが...)
明見谷(北側)方面の展望。
|
 |
その先右手に竪堀跡。
|
 |
そのすぐ先の郭跡。
|
 |
西の鞍部です。
完全に藪化して、藪の下は長雨の為湿地状態です。
西第二堀切(鳥越堀切)跡。らしいです。
|
 |
上記堀切の中を北へ下る。
登城路と思われる明見谷へ下る道だが、
今は途中から藪化して通れないのでは?...
|
 |
井戸跡。
|
 |
ここも...
|
 |
ここも...
|
 |
井戸の廻りに石積み跡。
|
(まとめ・総評)
武田一族小河内弥太郎の居城。
小河内弥太郎は武田刑部の弟。武田刑部は伴(沼田町)藩主で伴氏一族。
伴氏は安芸武田氏の分家で、武田を名乗ったともゆう。
牛頭山城は、武田氏が対大内氏を見据えて、銀山城の背後を守る為に築城し、一族を置いたとも...
本城は、牛頭山の西峰を中心に東西鞍部までの広範囲に、多くの郭、堀などを配してます。
標柱などでの説明もあり、登山道に加え、城跡としても整備されています。
(見落とした物もあると思いますが、確認した標柱は郭名を記述しています。一部「広島市の山を歩く」より。)
ひろしま昔探検ネットには、比高370mとありますが、これは明見谷中ほど辺りからの比高と思われます。
本ページでは、本城東側の鈴張川から計算して、比高580mとしています。
場所、登城路に関しては、コチラを参照!
今回で記念すべき100城目(同城訪問は未カウント)です。(^o^)/
|