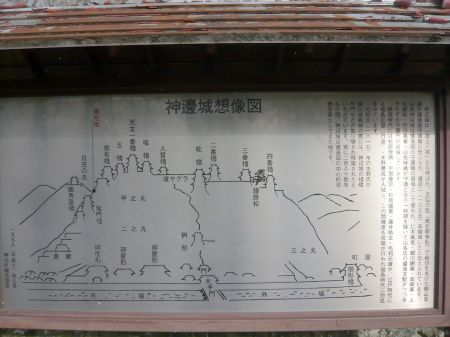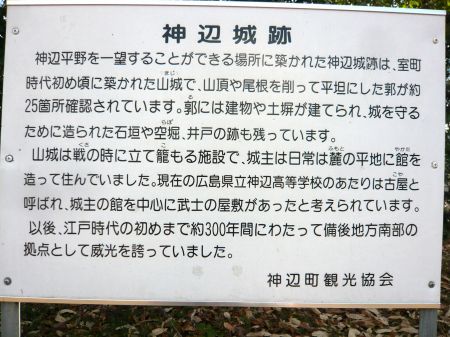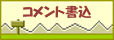|
神辺城跡に向う途中、南西方向より。
公園化で一部木が伐採されています。
この部分から右の樹林帯へ向けて、
畝状竪堀が20本以上連なっているはずですが、
伐採部分はもちろん、
樹林帯の中にも確認出来ませんでした。
|
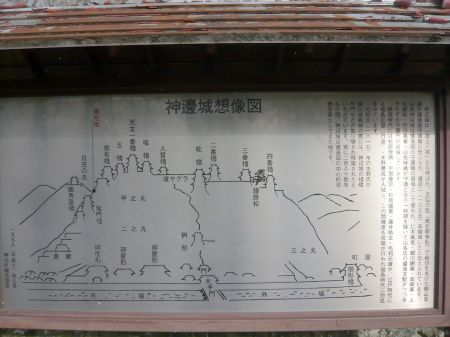 |
主郭郡東端まで車で上がれます。
そこの駐車場にある「神邊城想像図」。
|
 |
F郭へ向けて主郭郡南側が通路になっています。
まず橋を渡るのですが、
その橋の下が堀切になっています。
|
 |
F郭。
F郭から西下に2つ郭がありますが、
西に向って左手は建造物に占領され、
右手は藪だらけだったので写真は撮りません。
|
 |
F郭から西に向って、神辺平野。
この右手後方備前方面から、
前方府中方面に向けてが旧山陽道、
左手芦田川河口方面に向けてが新山陽道です。
海路交通が盛んになるに連れて、
要路も山間部から沿岸部へ移動しています。
|
 |
北側の展望。
高屋川を挟んで中央は、要害山城(天神山城)跡。
|
 |
E郭。
奥はD郭。
|
 |
D郭。
|
 |
C郭。
石積み跡が...
|
 |
B郭。
C郭、D郭を見下ろす。
|
 |
A郭南斜面の藪に分け入り、石垣跡。
|
 |
これも...
|
 |
これも...
これは比較的新しい時代のものでしょう。
|
 |
A郭。
|
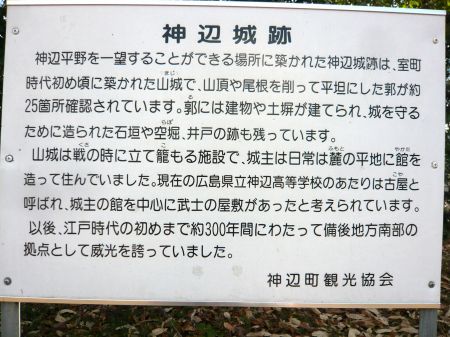 |
A郭にある案内板。
|
 |
A郭南東にある登城口。
|
 |
A郭北にある登城口。
|
 |
G郭。
|
 |
G郭にある井戸跡。
|
 |
G郭からH郭を見下ろす。
この尾根先にも郭郡がある様です。
今日は行きません。
|
 |
H郭にある石積み跡。
|
 |
H郭からG郭を見上げる。
|
 |
H郭から駐車場(堀切方面)に戻る途中、
搦め手の谷筋を見下ろす。
|
 |
搦め手(北東)側からの遠景。
|
(まとめ・総評)
1335年、備後守護に就いた朝山景連による築城。
1401年、山名氏が備後守護代に就く。
1538年、杉原理興が大内氏の命で尼子側の山名氏政、忠勝を追い、城主となり、以後山名姓を名乗る。
1542年、理興は大内氏の出雲遠征の情勢を見、尼子側に走り、対大内側との神辺合戦となる。
1549年、堅城神辺城も大内氏の総攻撃に耐え切れず、山名理興は出雲に走る。
その後理興は許されて神辺に復帰、1557年に病死し、同族の杉原盛重が毛利氏の後押しで城主となる。
(その間、陶隆房の謀反、折敷畑の戦い、厳島合戦を経て、備後は毛利氏の版図になる。)
1584年、杉原氏の内紛によって毛利氏により討伐、以後毛利氏の直轄となる。
1600年、関ヶ原敗戦後、福島正則入封、のそ筆頭家老福島正澄が入城。
1619年、福島氏改易後、水野勝成が入封。その後、神辺城は規模が小さい事から福山城を築き、移る。
これにより神辺城は役目を終え、廃城となる。
石積み跡と見られる石が各所で見られましたが、自然石らしきもの、加工石と織り交じり、長い歴史を感じます。
四角く加工された石や、矢穴のある石も多く見受けられました。
国道313号線神辺町川北で、黄葉山の北東の谷筋から「吉野山公園」又は「神辺城跡」を目指して車で登る。
突き当たりが神辺城跡の駐車場で、写真2枚目の看板がある。
写真1枚目の伐採部分につづら折りの階段も見られましたので、そこから歩いても登れるのでしょう。
本日5箇所廻った中の1箇所目です。
|